山上の垂訓(すいくん)はイエスの生涯(もしくは福音書)の中でも一つのピークを成すと思います。
その中でも僕が好きなのは「柔和な人たちは、さいわいである、 彼らは地を受けつぐであろう。」という一節です(マタイ5:5)
「柔和な者が地を受け継ぐ」というイメージが繰り返しリフレインします。
僕自身が感情的で、エキセントリックで、「柔和」とは程遠いからかもしれませんが(笑)
ちなみにこの山上の垂訓には名言として知られているものの宝庫です。
たとえば、冒頭の「心の貧しきものは幸い」は超有名です。
「こころの貧しい人たちは、さいわいである、天国は彼らのものである。」(マタイ5:5)、
続けて、
「あなたがたは、地の塩である。(5:13)」
「あなたがたは、世の光である。(5:14)」
など印象的なフレーズが次々と。
「世の光」については、真面目な教会牧師の先生が広い光り輝くおでこを示しながら、「あなたがたは、世の光である」とやってくださったという強烈な印象があります。
まさに言葉が肉体を持った瞬間に立ち会いました(「そして言は肉体となり」ヨハネ1:14)
*本文とは一切関係ありませんが、イグナチオ・デ・ロヨラです。僕らがセミナーやスクール中に聴く鐘の音は聖イグナチオ教会からです。
僕自身がよく引用するのは、イエスの言う律法を廃するためではなく、成就するためという17節です。
パラダイム・シフト論と重ねて議論します。パラダイム・シフトはパラダイムを破壊しようとするもののによってではなく、パラダイムを完成させようとするものによって起こります。
「わたしが律法や預言者を廃するためにきた、と思ってはならない。廃するためではなく、成就するためにきたのである。(5:17)」
そしてこれはスコトーマでしたが、地獄の火に投げ込まれないように、口を慎もうと思いますw
「また、ばか者と言う者は、地獄の火に投げ込まれるであろう。」(5:22)
親鸞にも似た話しがあります。
一つは師である法然に騙されたとしても「地獄こそが私の住処」(地獄は一定すみかぞかし)という激しい諦観。そして、弟子の唯円に対して言う、「オレの言うことが正しくて、いつでも聞けるというのであれば、今から人千人殺してこい」という話です。どちらも歎異抄です。
「もしあなたの右の目が罪を犯させるなら、それを抜き出して捨てなさい。五体の一部を失っても、全身が地獄に投げ入れられない方が、あなたにとって益である。」(5:29)
「もしあなたの右の手が罪を犯させるなら、それを切って捨てなさい。五体の一部を失っても、全身が地獄に落ち込まない方が、あなたにとって益である。」(5:30)
それに対して、本当に親指を切り落としてしまうという禅の考え方は(僕は好きですけど)違和感があります(無門関ですね「倶胝和尚(ぐていおしょう)は、誰が何を問うても、ただ一指を立てた」)。
というのも、釈迦はそうしただろうか?、と思うと、おそらくは否だからです。まあ所詮、公案なので、脳トレです。
続けます!
誓うな!というこの視点は非常に重要です。
「また、自分の頭をさして誓うな。あなたは髪の毛一すじさえ、白くも黒くもすることができない。」(5:36)
イエスにせよ、他の聖人にせよ、このメタファーと現実のつなげ方の鮮やかさが凄みです。
非常に分かりやすい言葉なのですが、その意味を本当に理解するには人生をかける必要があります。
あなたがたの言葉は、ただ、しかり、しかり、否、否、であるべきだ。それ以上に出ることは、悪から来るのである。(5:37)
あまりに有名な、右の頬を打たれたら、というくだり。同じことを手を変え品を変え、語ります。
まず頬。
もし、だれかがあなたの右の頬を打つなら、ほかの頬をも向けてやりなさい。(5:39)
そして着物。
あなたを訴えて、下着を取ろうとする者には、上着をも与えなさい。(5:41)
移動。
もし、だれかが、あなたをしいて一マイル行かせようとするなら、その人と共に二マイル行きなさい。(5:23)
その精神を煎じ詰めると、
求める者には与え、借りようとする者を断るな。(5:24)
となります。
そして隣人愛を誤解する人に対して、
敵を愛し、迫害する者のために祈れ。
そして、重ねて、
あなたがたが自分を愛する者を愛したからとて、なんの報いがあろうか。そのようなことは取税人でもするではないか。(5:46)
と語ります。
以下のくだりはユダの福音書を思わせます。
キリスト教会に唾棄され、最も迫害されたのはユダです。
そう思って、読むとまた新しい見方ができそうです。
単に殉教者たちを見るのではなく。
「義のために迫害されてきた人たちは、さいわいである、
天国は彼らのものである。」(5:10)
「わたしのために人々があなたがたをののしり、また迫害し、あなたがたに対し偽って様々の悪口を言う時には、あなたがたは、さいわいである。(5:12)
喜び、よろこべ、天においてあなたがたの受ける報いは大きい。あなたがたより前の預言者たちも、同じように迫害されたのである。(5:13)
山上の垂訓だけではなく、聖書自体は名言の宝庫であり、書物の書物です。
ただ聖書を読むためには、他の書物を読む必要があります。それだけ読んでも読めません。
まさに「薔薇の名前」でワトソンくんが言うように、
「書物は書物について語」り、それどころか「書物同士で語り合」うのです。「一巻の書物が述べていることを知るために、別の書物を何巻も読まなければいけない」のです。
しかし、逆にそのネットワークが稠密になり、また質が上がる(抽象度が上がる)ことで、読みは深くなります。読みが深くなる瞬間というのは、逆説的ですが、これまでの自分の読みの浅さに気付かされる瞬間でもあります。「あ、間違っていた」もしくは「これまでの読みが浅かった」と気づくときに、抽象度が上がります。逆に、抽象度が上がることで、これまでの無意識の前提なり、読み方が相対化されます。
それこそが人生の喜びかと思います。その喜びは書物の中にあるのではなく、宇宙の中にあります。
*薔薇と言えばヘーゲルですね。 最近、寺子屋でやったばかりです。
「ここがロードス(島)だ、ここで跳べ」というイソップ物語を変形して、「ここがローズ(バラ園)だ、ここで踊れ」と言い、それに付け加えてこう語ります。
「理性を現在の十字架における薔薇として認識し、それによって現在を喜ぶこと。この理性的な洞察こそ、哲学が人々に得させる現実との和解である」(法の哲学)
「薔薇の名前」をもじるならば、この1行を理解するには、何冊もの古典が必要です。
ちなみに、なぜ「ここがロードスだ、ここで跳べ」が「ここがローズだ、ここで踊れ」になるのかと言えば、「ギリシャ語のロドス(島の名)をロドン(ばらの花)に、ラテン語のsaltus(跳べ)をsalta(踊れ)に「少し変え」たしゃれ。」と「世界の名著 ヘーゲル」の注にはあります。ギリシャ語とラテン語に通暁していないと、ニヤリとできないシャレですね。
【書籍紹介】
薔薇の名前〈上〉/東京創元社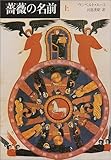
¥2,484
Amazon.co.jp
薔薇の名前〈下〉/東京創元社
¥2,484
Amazon.co.jp
薔薇の名前 The Name of the Rose [Blu-ray]/ワーナー・ホーム・ビデオ
¥2,571
Amazon.co.jp
法の哲学〈1〉 (中公クラシックス)/中央公論新社
¥1,620
Amazon.co.jp
↧
「ここがローズ(バラ園)だ、ここで踊れ...理性を現在の十字架における薔薇として認識し...」
↧