あまりに印象的な薔薇(バラ)を見てしまったので、ついウンベルト・エーコの「薔薇の名前」を読み返してしまいました。
「薔薇の名前」は最後の一言があまりにも有名です。
stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
(以前の薔薇は名に留まり、私たちは裸の名を手にする)(Wikipedia)
翻訳はWikipediaのもので、形式的に訳すとこうなると書かれていますが、ちょっと意味不明です。「裸の名」って何でしょう。名前のエリクシール(本質)でしょうかw
ちなみに「薔薇の名前」の邦訳ではこうあります。
〈過ギニシ薔薇ハタダ名前ノミ、虚シキソノ名ガ今二残レリ〉
ちなみにこの邦訳ではラテン語の部分はあえて「たどたどしい日本語」へ訳しているそうです。それもカタカナで。
かってにひらがなに戻すと、「過ぎにし薔薇はただ名前のみ、虚しきその名が今に残れり」となります。
ご承知のように「薔薇の名前」は本好きの人にはたまらない物語です。たしかに一見するとホームズとワトソンの物語(推理小説)ですが、その謎解き以外の書籍から書籍に渡る謎解きのほうが面白すぎます。そしてその謎の深淵を垣間見ることで、何か本質的なものがそこに表れているような期待感があります(いや、少なくとも僕はそう確信しています)。
セミナーでは何度となく「薔薇の名前」について言及しています。
ブログでも書いているのではと思い、ブログ内検索をしてみると、「これからアメンバー記事しか書かないことについてとアメンバー申請について
2013-02-05」という記事で、「薔薇の名前」について言及しています。
(引用開始)
ちなみに、これは今年の1Dayスクールでウンベルト・エーコの薔薇の名前を引いたときにレジュメに使おうと思った画像の1つです(結局はもう1つの真紅のバラの写真を使いました)。
「薔薇の名前」のラストですね。
某大学の昨年でしたか入試問題にこのラテン語を英語にしなさいという問題が出ました。
stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
以前の薔薇は名に留まり、私たちは裸の名を手にする(Wikipediaより)
1Dayスクールではクリプキの「名指しと必然性」と絡めながら、この言葉の解釈を少し考察しました。
スクールが終わったときは一面の雪でしたね。(引用終了)
某大学というのはICUのことです。
受験生諸君に「薔薇の名前」くらいは読んでいるよね、ってことなのだと思います。
さすがリベラル・アーツを標榜するだけはあります。
高校生にラテン語くらいはできるよね、ってことではないと思いますw
もしくはどちらもできなくても、その場で見出だせるよね、ってことでしょう。
クリプキ様の「名指しと必然性」とどう絡めて、この薔薇の名前を解題したのかは全く覚えていませんが、深夜過ぎまでやっていた1Dayスクールはうっすらと覚えています。夜半に雪が積もっていました。
このころはあまりに批判されることに疲れて、「じゃあ読まなきゃいいじゃん」などとも言えず(言ったかもしれませんが)、じゃあ全部アメンバー記事にします、という時期でした。ブログを閉じようと真剣に悩んだ時期でした。
嵐が過ぎ去って(もしくは嵐の渦中にいることに慣れたのかもしれません)、通常の記事で書くようになり、その後かなりアメンバー解除しましたが、まだアメンバーとして残っているのはたくさんあります(アメンバー記事はあまりにパソコンで表示したときの画面が簡素というか、ひどすぎて、それが嫌です。スマホなら変わらないのですが)。
まあ、それはさておき、薔薇の名前です。
そのラストセンテンスです。
stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
まずラテン語から考えましょう。
とは言え、ググってみると、いくつか出てきます。
*stat:sto,stare(【動】立っている、存続している、留まる)の3人称単数現在:主語はrosa。
*pristina:pristinus(【形】原初の、以前の)の女性単数形。
*nomine:nomen,-minis(【中】名前)の単数奪格。
*nomina:nomenの複数対格;tenemusの目的語。
*nuda:nudus【形】裸の;単なる、ただの)の複数対格。
*tenemus:teneo,-ere(【動】握る、保持する)の1人称複数現在。
http://blog.livedoor.jp/erastos8136/archives/51782453.html
stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
とは荒削りには、statはstand, rosaはrose, pristinaはformer, nomineとnominaは格変化しているだけでname,nudaはnude,tenemusはhaveやholdです。
stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
stand/ rose/ former/ name,/ name/ nude/ hold
ですので、「過ぎにしバラはただ名前のみ、虚しきその名が今に残れり」「(以前の薔薇は名に留まり、私たちは裸の名を手にする)」も分かるような気がします(分かるような気がするというのは不遜に聞こえる言い方ですが、他意はありません)
tenemusが1人称複数現在なので、「我々はいま持っている」ということです。
この最後のラテン語の引用は修道士モーレーの六脚韻詩です。
幸いにもホイジンガの名著「中世の秋」に同じ詩からの引用があります。
ホイジンガの文脈の中で見ていくと、これは死について語っていることが分かります。
非常に短絡的に言えば、「虎は死して皮を残し、人は死して名を残す」という感じです(違うかっ)。
中世の秋から引用します!
(引用開始)
バビロンの栄華は、いまいずこに、いずこにありや、かの恐るべき
ネブカドネザル、力みてるダリウス、また、かのキルスは。
力もて押されてまわる車輪のごと、かれらは過ぎゆきぬ、
名は残り、たしかに知られるも、かれらは腐りはてぬ。
今は昔ぞ、カエサルの議場、また凱旋。カエサル、汝(なれ)も失(う)せにき。
あらあらしくも世界に力ふるいたる御身なりしが。
・・・・・・・・・・・・
いまはいずこ、マリウス、また廉直の士ファブリキウスは。
パウルスのけだかき死、その称(たと)うべき軍功(いさお)は。
デモステネスの神の声、またキケロの天よりの声は。
市民へのカトーの祝福、また、逆徒への怒りは。
レグルス、いまいずこに、また、ロムルスは、レムスは。
きのうのばらはただその名のみ、むなしきその名をわれらは手にする
(引用終了)
(ホイジンガ 中世の秋Ⅰ 堀越孝一訳 中高クラシックス pp.335-336)
引用の最後の一節がまさに「薔薇の名前」のラストです。
「きのうのばらはただその名のみ、むなしきその名をわれらは手にする」
うーん、この訳が一番ピンと来る感じがします。
ここでの主題はシンプルです。「おごれる人も久しからず」ってことです。
あんなに一世を風靡しても、いまはもう名前しか残っていないじゃん!という虚しさを歌っています。
ちなみに冒頭の「バビロンの栄華は、いまいずこに、いずこにありや、かの恐るべき
ネブカドネザル」
というのは寺子屋「悪魔学」でやったばかりですね。
いわゆるルシファーです。堕天使でのちのサタンとされるルシファー(ラテン語で明けの明星)です。
そもそも旧約聖書で明けの明星と譬えられたのは、バビロニアの王様であるネブカドネザルです(マトリックスの母船の名前です)。それがなぜか「おごれる人も久しからず」、おごれる人は転落するということと、サタンが堕落したということを重ね合わせて、アウグスティヌスたちが、ルシファー(明けの明星)はサタンであると認定しました。
ネブカドネザルも真っ青です。
平氏が閻魔様になったようなものです(悪魔学はそんな物語で満ち満ちています)。
まあ、それはさておき、ここでの大きなテーマは死です。
ですから、「きのうのばらはただその名のみ、むなしきその名をわれらは手にする」とは、死について語っています。より具体的には、栄華をほこったバビロニアの王もいまはその名前しか残っていない(ああ、なんて虚しきこと!)ということです。
ホイジンガの「中世の秋」から少し引用します。
(引用開始)
十五世紀という時代におけるほど、人びとの心に死の思想が重くのしかぶさり、強烈な印象を与え続けた時代はなかった。「死を想え(メメント・モリ)」の叫びが、生のあらゆる曲面に、とぎれることなくひびきわたっていた。ドニ・ル・シャルトルーが、その著『貴族生活指導の書』のなかで、貴族たちに説きすすめていうには、「ベッドに横になるとき、想うがよい、いまこうしてベッドに横たわっているように、じきにこのからだは、他人の手で、墓のなかに横たえられることになるのだと」(略)
この死のイメージ、これは、およそ死ということに関連して実にたくさんある、さまざまな考えのうち、たったひとつを表現するものにすぎなかったのである。すなわち、無常の観念を。あたかも、中世末期の精神は、ただ、人生無常との観点からしか、死を考えることを知らなかったかのようなのだ。
すべて、この世のおごりには終りがあるとの、永遠につきない嘆きをかなでる三つのメロディーがあった。第一のメロディーをかなでるのは、かつてその栄光一世を風靡した人びとは、いまいずこにある、というテーマ。第二のメロディーをかなでるのは、ひとたびは、この世の美とうたわれたものすべてが、腐り崩れていくさまをみて恐れおののくというテーマ。そして、第三に、死の舞踏のテーマ、この世のなりわいを問わず、老幼の別なく、死はすべての人を引きずりまわす、という。
後二者のテーマの、胸をしめつけるような恐ろしさにくらべれば、むかしの栄華、いまいずこ、というテーマは、悲歌ふうの軽い嘆息にすぎないのだ。(ホイジンガ「中世の秋Ⅰ」pp.333-335)
ざっくり言えば、「十五世紀という時代におけるほど、人びとの心に死の思想が重くのしかぶさり、強烈な印象を与え続けた時代はなかった。」わけで、ただその死のイメージは単調で死とは無常というものでしかなかった、と。
中世=「死の思想」(メメント・モリ=死を忘れるな)
死=人生の無常
そして、そのテーマを3つに分けると、第一に一世を風靡した人はいまいずこ?、第二は九相図(屋外にうち捨てられた死体が朽ちていく経過を九段階にわけて描いた仏教絵画)、第三は死の舞踏(、死の恐怖を前に人々が半狂乱になって踊り続ける)です。
九相図はさすがにグロいので、戯画的な死の舞踏の絵画と美しい音楽を。
繰り返してホイジンガをまとめると、
中世=「死の思想」(メメント・モリ=死を忘れるな)
死=人生の無常
1.驕れる者は久しからず
2.九相図
3.死の舞踏
ということになります。
で、
薔薇はこの1つ目の話しです。
ウンベルト・エーコの「薔薇の名前」を紐解いてみると、ラストの二段落前にこうあります。
しかしこのように私の目が効かなくなってしまったのは、おそらく、忍び寄ってくる大きな闇が年老いたこの世界の上へ投げかけつつある暗い影のせいであろう。
〈バビロンノ栄華ハイマドコニアルノカ?〉去年(こぞ)の雪はいまどこにあるのか?大地は死の舞踏を踊り続け、ダニューブの流れも小暗い場所へ向けて進みゆく愚者の群れの船に満ちている、私にはしばしばそう思えてならない
〈バビロンノ栄華ハイマドコニアルノカ?〉とはまさにラストの引用に対応しています。
同じ詩の冒頭なので。
この語り手(中世世界の修道士)は死の恐怖と死の闇について語り続けます。
ですから、素直に読むならば、この「きのうのばらはただその名のみ、むなしきその名をわれらは手にする」というのは、私もまた死に飲み込まれるという意味でしょう。
とは言え、そこからまた無限ループのようなこの「薔薇の名前」という小説の文書館のような迷宮に入っていきます。
こんな単調な理解をあざ笑うのがこの小説の素晴らしいところです。
とは言え、これ以上踏み込むのはかなりのネタバレを含みます。推理小説である以上はネタバレは避けたいところです(まあ、有名な物語なので、読んでいらっしゃるとは思いますが)。
ただこの物語自体が中世のお話しではなく、現代の我々に響く何かを持っていることは事実でしょう。
我々の「いま」の問題に強く響きます。そんな部分を少しかいつまんで紹介します。
たとえば、ホームズとワトソン(修道士の先生と生徒)のこんな会話があります。
まずは中世のホームズことウィリアムの嘆きから。
見事な推理を披露したにも関わらずウィリアムは苦しみます。
「一連の原因の鎖が、原因から派生した原因の鎖が、相互に矛盾する原因の鎖が、つぎつぎにたぐられていくと、それらが勝手に独り歩きをして、初期の企みとは無縁な別個の諸関係を生み出してしまうのだった。わたしの知恵など、どこに居場所があろうか?わたしは頑なに振る舞っただけのことだ、見せかけの秩序を追いながら、本来ならばこの宇宙に秩序など存在しないと思い知るべきであったのだ」
「本来ならばこの宇宙に秩序など存在しないと思い知るべき」というのは辛い叫びですが、我々はチャイティンのこんな叫びを思い出します。
科学と魔術とは、通常の現実が本当の現実ではない、日 常の見かけの後ろにより基本的な何かが潜んでいるとい う信念を共有しています。どちらも、隠れた秘密の知識 の基本的な重要性に関する信頼を共有しています。物理 学者は、万物理論(TOE)を探し続けています。そして、 カバラ信者は、あらゆることの理解の秘密の名前を探し 求めています。ある意味で、両者は仲間であり、どちら も、秘密の意味は存在しないとか、最終理論はないとか 言う考えには耐えられません。そして、物事が全く任意 で、ランダムで、無意味で、圧縮不能で、理解不能であ るという考えに耐えられません。(「知の限界」チャイ ティン p.129)
これは言い換えれば「この宇宙に秩序など存在しない」という意味です。
ゲーデルの不完全性定理をLispによって数学全体に拡張して証明してしまったチャイティンらしい、懺悔にも聞こえます。
ゲーデルの不完全性定理自体は、神なり神学を支えていた信念を根本から破壊しました。
アプリオリは否定された、神は死んだ!とニーチェのように叫ぶのは自由ですが、その絶望感はきちんと味わうべきかと思います。
逆に、よくゲーデルの不完全性定理が否定した「神」は全知全能の神であって、不完全な神は否定されていないという人がいらっしゃいます。まあ、それはそれで良いのですが、その神とやらは鉄腕アトムとか、アラレちゃんとか、進撃の巨人と同じような存在です。
八百万神(やおろずのかみ)とか、ギリシャ神話の神は矛盾を含んでいるからゲーデルの不完全性定理は通用しないとか、よくわからないことをおっしゃる方もいますが、それは良いとして、そこまでなぜ我々が退化しなくてはいけないのかについて、きちんと考えるべきでしょう。
いまさらそのような多神教の神を信仰するところまで戻れるのでしょうか?
禁断の果実を食べたら、楽園は追放されるのです。
知識をひとたび得ると我々はもうそれ以前の状態にもどれないのです。
それはさておき、続けます。
(引用開始)
「見せかけの秩序を追いながら、本来ならばこの宇宙に秩序など存在しないと思い知るべきであったのだ」
「誤った秩序を想像したのかもしれませんが、やはり発見なさったものがあったではありませんか・・・・・・」
「お前はとても良いことを言ってくれた、アドソ、おまえには感謝するよ。わたしたちの精神が想像する秩序とは網のようなもの、あるいは梯子のようなもので、それを使って何ものかを手に入れようとするのだ。しかし手に入れたあとでは、梯子は投げ棄てなけらばならない。なぜなら、役には立ったものの、それが無意味であったことを発見するからだ。Er muoz gelichesame die leiter abewerften. so er an ir ufgestigen[昇りきった梯子は、すぐに棄てなければいけない]」(p.372)
(引用終了)
投げ棄てるではなく、聞き捨てならない言葉ですw
もちろんこれはウィトゲンシュタインを想起させます。
「いわば、梯子をのぼりきった者は梯子を投げ捨てねばならない(論理哲学論考命題6.54)」
です。
前後を含めて引用するとより明確でしょう。
(引用開始)
語りうること、すなわち自然科学の命題--すなわち哲学とはなんの関係も無いこと--以外は何も語らぬこと。そして誰かがなにか形而上学的なことを語ろうとした時、そのたびに、あなたはあなたの命題のこの記号にいかなる意義も与えていないと指摘する。これが、本来の正しい哲学の方法である。この方法はその人を満足させないだろう。--彼は哲学を教えられている気がしないだろう。--しかし、これこそが、唯一厳密に正しい方法なのである。(6.53)
私を理解するひとは、私の命題をよじ登り--その上に立ち--それを乗り越え、最後にそれがナンセンスであると気づく。このようにして私の命題は解明的である。(いわば、梯子をのぼりきった者は梯子を投げ捨てねばならない。)
私の命題を超えねばならない。その時世界を正しく見るだろう。(6.54)
語りえぬことについては,沈黙するしかない。(7)
(引用終了)
*ウィトゲンシュタインのお墓にある梯子です。もちろん論理哲学論考をふまえての梯子。投げ捨てるべき梯子です。
「語りえぬことについては,沈黙するしかない」という印象的なラストセンテンスが有名ですが、その直前の梯子のくだりも印象的です。
「私を理解するひとは、私の命題をよじ登り--その上に立ち--それを乗り越え、最後にそれがナンセンスであると気づく。」と書いています。
すなわち命題をよじ登ったあとで、それを乗り越えたら、それがナンセンスであると気づくので。
「それが無意味であったことを発見する」に対応しています。
これは名前を思い出せない中世の「ある神秘主義者」の言葉(「薔薇の名前」)ではなく、ウィトゲンシュタインを意識しているように思います。著者のエーコ自体が記号論の人なので当然と言えば当然なのかもしれませんが。
美しい薔薇からスタートして、話しは止まらないので、ひとまずここで閉めます。
【書籍紹介!】
薔薇の名前〈上〉/東京創元社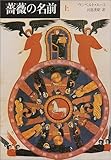
¥2,484
Amazon.co.jp
薔薇の名前〈下〉/東京創元社
¥2,484
Amazon.co.jp
薔薇の名前 特別版 [DVD]/ワーナー・ホーム・ビデオ
¥1,543
Amazon.co.jp
中世の秋〈1〉 (中公クラシックス)/中央公論新社
¥1,620
Amazon.co.jp
中世の秋〈2〉 (中公クラシックス)/中央公論新社
¥1,512
Amazon.co.jp
知の限界/エスアイビー・アクセス
¥3,024
Amazon.co.jp
論理哲学論考 (岩波文庫)/岩波書店
¥778
Amazon.co.jp
↧
きのうのばらはただその名のみ、むなしきその名をわれらは手にする
↧