ウンベルト・エーコの「薔薇の名前」について引き続き、いくつか言及します。
「薔薇の名前」という名前自体は誤解を招きます。どう誤解を招くかと言えば、原題はいわば「「その薔薇のその名前」だからです。日本語では冠詞は意識されないので、ツルッとしてしまいますが、冠詞でゴツゴツとしたタイトルです。
そもそもはイタリア語で「Il Nome della Rosa」で、英訳も「The Name of the Rose」です。
イタリア語はさっぱり分からないなので、ググってみると、"il"は単数の男性名詞に付く定冠詞でいわば「The」にあたり、「della」は前置詞「di」+冠詞「la」(女性詞単数)だそうです。ですので、della は英語のof theにあたるということですね
まあ、英訳がはっきりしています。NomeにもRosaにも定冠詞がついているという点がポイントでしょう。
まさに「The Name of the Rose」ですね、強引に日本語に訳するなら「その薔薇のその名前」ということになるかと思います。
そう訳すと、このタイトルが意味するのは、あの恋人である者の名前という(それも生涯唯一の、そして名を知らぬ)解釈が妥当に思えてきます。The Name of the Roseです。その薔薇(にたとえるべき女性)のその名前ですね。
そして、「きのうのばらはただその名のみ、むなしきその名をわれらは手にする」が最後に来るのは、もう二度とその少女に会うことがが叶わなく、知らぬ名を思って死に至る心境なのかもしれません。
もちろん「むなしきその名」すら知らないのですが、ここで言う「名」とは記憶や面影という理解で良いかと思います。具体的な名前は知らなくても、名前があることは知っているので。
「薔薇の名前」は主要なテーマは悪とは何か?です。
これは中世の当時もそして現代も大きな問題です。異端による火炙りにされる世界ではないですが、抽象度の高い空間に移動して、ネットでまさに炎上することで命を断つ人もいます。社会的生命も抹殺されることもあります。
それはともかく「薔薇の名前」における悪の結論は明瞭です。
悪魔学との結論とも照らし合わせながら、楽しめると思います。
ウィリアムことホームズによる結論です。
(引用開始)
悪魔は物質界に君臨する者ではない。悪魔は精神の倨傲だ。微笑みのない信仰、決して疑惑に取り憑かれることのない真実だ。(引用終了)(「薔薇の名前」下巻p.350)
まとめると
悪魔 = 精神の倨傲、微笑みのない信仰、決して疑惑に取り憑かれることのない真実
です。
続けてこう言います。
反キリストとはアンチキリストとも言いますが、悪魔の別名です。
キリストのダークサイドというか、キリストのアンチテーゼですね。
ウィリアムはアンチキリストの顔を見た、と主張します。そこからこんな結論を引き出します。
(引用開始)
哲学への憎悪に歪んだ。あの顔のなかに、わたしは生まれて初めて反キリストの面影を見た。それは、彼の到来を預言した者たちが言うように、ユダの一族から来た者でもなければ、遠い国からやってきた者でもない。反キリストは、ほかならぬ敬虔の念から、神もしくは真実への過多な愛から生まれてくるのだ。あたかも、聖者から異端者が出たり、見者から魔性の人が出るように。(引用終了)(同p.370)
悪魔は「ほかならぬ敬虔の念から、神もしくは真実への過多な愛から生まれてくる」と言います。
「神もしくは真実への過多な愛」です。
これが「微笑みのない信仰」「決して疑惑に取り憑かれることのない真実」ということです。
これだけではよく分からない場合は、対概念を取り上げます。
すなわちウィリアムにとっての真理とは、を考えます。
それは「笑い」と関連します。
(引用開始)
おそらく、人びとを愛する者の務めは、真理を笑わせることによって、真理が笑うようにさせることであろう。なぜなら、真理に対する不健全な情熱からわたしたちを自由にさせる方法を学ぶこと、それこそが唯一の真理であるから(引用終了)(pp.371-372)
真理を笑わせるとか、真理が笑うという真理の人格化というメタファーにはついていけない面がありますが、「真理に対する不健全な情熱からわたしたちを自由にさせる方法を学ぶ」という点は大きくうなづけます。
不健全な情熱というのがまさに精神の倨傲であり、微笑みのない信仰、疑惑に取り憑かれることのない真実です。
真理を得たと確信して、その真理の無謬性を疑わないとしたら、それは魔に堕ちるということです。
ただ単にすべてをデカルトのように疑えというのではなく(デカルトは疑い得ないものを得ましたが)、むしろ真理を笑えと言います。
非常に卑近な例に引き寄せて理解するならば、どの真理にもその核心にその体系全体を否定するようなアンチテーゼが(アンチキリストではなくw)存在するということでしょう。そう考えると、きわめてヘーゲル的です。
そうすると、その立場を取ると、ホームズとワトソンの二人が最後に繰り広げた神学論争のように(それは大音響と共に中断され、再開することがありませんが)、知識の完全性は損なわれ、神の存在証明も失われるという結論にならざるを得ません。
すると我々は神話学の世界、もしくは物語が物語を呼び、新しい物語を重ねていく世界(エーコが「薔薇の名前」で描こうとした世界)が眼前に広がるのではないかと思います。
リンゴという単純な言葉ですら、様々な物語がそこから引き出せます。ましてや書物をや、です。
二人のこんな会話がかわされます。
(引用開始)
「なぜですか? 一巻の書物が述べていることを知るために、別の書物を何巻も読まなければいけないなんて?」
「よくあることだよ。書物はしばしば別の書物のことを物語る。一巻の無害な書物がしばしば一個の種子に似て、危険な書物の花を咲かせてみたり、あるいは逆に、苦い根に甘い実を熟れさせたりする。アルベトゥスを読んでいるときに、後になってトマスの言うことが、どうして想像できないであろうか?あるいはトマスを読んでいるときに、アヴェロエスの言ったことを、どうして想像できないであろうか?」
「そうですね」私は関心してしまった。そのときまで書物はみな、人間のことであれ神のことであれ、書物の外にある事柄について語るものだとばかり思っていた。それがいまや、書物は書物について語る場合の珍しくないことが、それどころか書物同士で語り合っているみたいなことが、私にもわかった。 」(引用終了)p.52 下巻
まさに書物は書物について語り、むしろ書物同士で語り合っているがごとくです。
書物は書物の外にある事柄について語ると考えてしまうと、先に結論を知りたくなります。しかしその結論の意味は全くなく、語り合うことに本来は意味があります。
なぜなら、「薔薇の名前」の冒頭にもあるように、「はじめにロゴスありき」(ヨハネ福音書)だからです。はじめにロゴスありきとは、逆に言えば、宇宙にはそれしか無いということです。
かつての定常宇宙論のように、真空から何かたとえば水素原子が生じるわけではないからです。追加されてくるわけではないのです。
すなわち、世界は言語でできており、その言語がお互いに呼応することでぼんやりと意味らしきものを浮かび上がらせるからです。少なくとも我々は言語宇宙しか観ることができません。
*「薔薇の名前」シリーズの最後は普遍論争についてです!
薔薇の名前〈上〉/東京創元社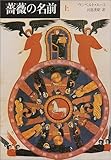
¥2,484
Amazon.co.jp
薔薇の名前〈下〉/東京創元社
¥2,484
Amazon.co.jp
薔薇の名前 特別版 [DVD]/ワーナー・ホーム・ビデオ
¥1,543
Amazon.co.jp
↧
薔薇の名前(Il Nome della Rosa)
↧